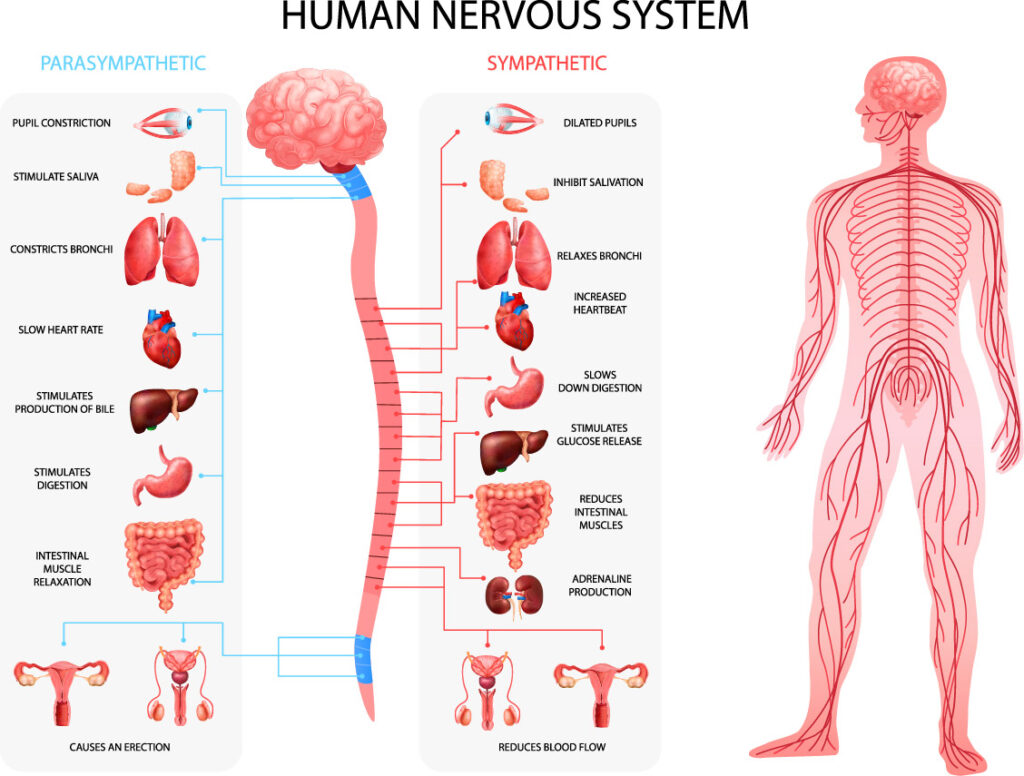傷つく原因
良かれと思っていったわけでも、悪意があっていったわけでもない言葉や行動で、明後日の方向から球が飛んでくるんだな、というお話。
昨日学童に子供を迎えに行ったら、指導員に呼び出された息子が何やら指導されている最中でした。外で15分ほど待っていたのですが、指導が終わって指導員さんが私に事の経緯をお話してくれた時、あ~・・・な経験をしました。
小学一年生の子の親御さんから「〇君(うちの息子)のことが怖くて学童に行きたくないとうちの子が言っている」という相談が学童にあったそうです。話を聴くと、金曜日にその子はうちの子に「ファッキュー」の中指を立てるしぐさをされたと言っているらしく。そうされる心当たりを指導員がその子に聴くと「〇君が遊ぼうって誘ってくれたのに僕が宿題やってるから無理って断ったからかなぁ…違うかもしれない、よく覚えてない」と。
そもそも息子はその子と学年も違えば一度も遊んだことがなく、遊びに誘ったこともないから、指導員がどういうことなのか息子を呼んで状況を聞いたそうです。
息子曰く「金曜日は教科書を忘れちゃって朝からイライラしていて、学童で宿題もできなかったからまたイライラして、一人で自分に向けてファッキューしていた。その子がそこにいたなんて知らなかった。自分のイライラを指で表現していた。それは誰かに対してやったわけじゃなくて、自分に対してやっていた」ということでした。
何回か息子がやっているのを観たことがあるのですが、派手に中指を突き立てるような分かりやすいファッキューではなく、左手のひらでファッキューの右手の指を隠しながら腰のあたりで小さく自分自身に向けてやるカタチです。指導員が再現してくれた時も息子のやり方でジェスチャーしていました。
つまり、その子のことは視界に入っていなかったけれど、その子は自分に対してシネと言われたように感じて傷ついたわけです。
誤解されるような強いネガティブなジェスチャーをした息子は、その部分において問答無用、全面的に良くなかったと思います。そして、それはしてはいけないと教えてはいましたが、自分のイライラの処理の仕方をきちんと教えていなかった私も良くなかったなと思います。
ここで、この出来事をシータヒーリングの観点から、二つの視点で整理しましょう。その子の主観と息子の学びの視点です。
被害者意識
その子は何故、息子のファッキュージェスチャーに対して自分に向けてやられている!と被害者意識を持ったのでしょうか。話しかけられた記憶がないのに、自分が遊びの誘いを断ったからやられたのかもしれないと思ったのでしょうか?自分に原因があるのではないかと疑って悩んだのでしょうか。
日常生活で、いつもいつも周りに気を使っていたり、自分の本心を尊重してもらえない場合、なにか目の前で起こると「自分が悪いのかな?何かしちゃったのかな?」と、自分に原因があるかのような罪悪感で物事を捉えるようになるかもしれません。
この子の親御さんが一方的に自分の子供が被害に遭った、という立場で指導員に訴えたことからも、遺伝的に被害者意識のビリーフがあるのだろうなと思います。もし親が自分のイライラを「あーもう!」と爆発させていて、その姿を見ていたらこどもは「僕が悪いのかな?」といつも自分のせいだと考える癖がついてしまうだろうなと思います。
この子と親御さんは被害者役を演じることで何を学ぼうとしていたのでしょうか。被害者でいることで何のモチベーションを得て、どんなメリットがあってそうしているのでしょうか。これがその子の立場から考える視点です。
人は、自分のエネルギーフィルターを介して物事をジャッジするから、時にそれが真実ではなくてもその人の中の真実になります。最高の真実はなに?何が本当なの?という視点を持つための学びもあるんだろうなと思います。自分以外の人の感じ方や考え方、行動の意味を自分の主観で決めつけるのは危険、ということは大人でも学べていない場合が多いので、その子はこれを人生通して学んでいくんだろうなと思います。
感情の処理の仕方
一方、息子の学びは何だったのか。
息子は自分が教科書を忘れてしまい学童で宿題が出来ずにイライラした気持ちの処理の仕方が分からずに、ファッキュージェスチャーを自分に対して行う=自分を責める、というやり方で底流が処理しようとしました。ここです。「感情の処理の仕方が分からない」「自分を責めるやり方をしてしまう」この部分が被害者役をやったその子と息子の共通点です。だからお互いに何かを学ぶために共同創造して今回のドラマを創造しました。
息子に事情を聴くと、「教科書を忘れて宿題できなくてイライラして、自分はダメだなと思って余計にイライラした」と言いました。つまり自分を責めたわけです。これは言葉を変えれば誰もが日常的にしている「後悔」です。あの時時間割をもう一回確認すればよかった、ママに忘れ物ない?って聞かれて「うるさいな!」って反抗的にならずに素直に聴いて確認すればよかった」その後悔で自分を責めたわけです。
そこで息子に教えました。後悔は持ってもいい。でも自分を責める形で後悔し続けることは、その場に立ち止まって足踏みし続けることで、一歩も前に進めない。だから失敗したら自分を責める方向にエネルギーを使うのではなく「この後悔を経験したことで学べたことは何?」って方向転換して、この後悔をしたから次は学べたことを生かして失敗しなくなった!前進できる!っていう方向にエネルギーを使ってごらん、と。
そして、息子から出てきた学べた良いことは「素直さ」でした。
ママや先生が確認してご覧といったことは素直に受け取って確認したら忘れ物しない、と。
それで息子に伝えました。ママも先生たちも、どうせ忘れ物するんだろうと決めつけたりなんかしていないし、どうせできていないと君を責める気持ちで「確認したら?」とは言ってないから、そこは誤解しないように。それって、1年生の子がやった「被害者意識」と同じだよね。そうじゃなくて、愛があるから、君が困らないように「確認して観たら?」って伝えてるだけ。だからママは、伝えた後ランドセルの中点検していないでしょう?必要があればちゃんとやるし、なにか学ぶことがあるなら忘れ物するし、君は自分にとって必要な行動をするからいいや、と信頼してるから」と伝えました。
そして、感情を認知することを教えました。幼い子供は今自分が怒っているのか、喜んでいるのかをメタ認知するということを知りません。だから、怒りや後悔や悲しみなどが出てきた場合は、「今僕は悲しいんだ」「今僕は怒ってるんだ」「今僕は後悔してるんだ」と認識する練習をしようねと。
その感情を持っていることが客観的に分かったら、その感情を持つことでどんなモチベーションになっているのか?何を正そうとしているのか?何を得ようとしているのかなどが分かります。まだ、何を学ぼうとしていたかは年齢的に自分で気づけないかもしれませんが、後悔の感情は単純に学びの内容が分かりやすいので今回話をして「創造主に変えてもらうのってここだよ。自分に対する怒りの感情を使って何を正した?何を学べた?かが分かったら、怒りを使わずに正す方法や、後悔をしなくても学べる方法を創造主が教えてくれて、新しいやり方に変えられるんだよ、と伝えました。
被害者意識を持つことで何を得たの?それも変えようか、と。
翌朝、つまり今日ですが、朝起きて「忘れ物ない?」と聞くといつもは「大丈夫だよ!」とうるさそうに強い口調で返してきますが「・・・あ!やっべぇ!」と言いながら何かをランドセルに入れていました。そして、学童では怖がらせてしまった子にごめんねを言ったそうです。
人は、鏡のように共通点がある人と共同創造しやすいです。波長が合うから共同創造します。学べるからです。息子の場合はその子と同じ「感情表現の仕方が分からない」「被害者意識を持っている」「自分のパラダイムで相手の行動の意味付けを決めつける」という共通項があったから今回学べたのだと思います。その子に感謝だね、と言うと「本当だね」と返ってきました。
誰かの言動や自分自身の行き場のない言語化できない感情に圧倒されたとき、人は表に攻撃的なエネルギーを出すこともありますが、自分を責めることもあります。でも被害者意識を持つということは、相手を加害者役に決めつけることで、それはある程度楽な自分への癒し方かもしれませんが、長くは続かない。そのやり方は、人生に自分を被害者役にしてくれる加害者役を量産します。引き寄せます。
後悔して自分を責めて罪悪感を感じ続けると、自己肯定感・自己効力感がどんどん削られます。自分で自分の自尊心を木っ端微塵にします。
だから何かが起こったら「今どんな感情なのかな、この状況を通して何か学べるとしたら何かな、この感情を強く持ち続けることで何のモチベーションになってるのかな」と考えることは、ネガティブな感情に留まり続けることなく人生を先に進められる手段になります。そして、相手を加害者役に自分の解釈で任命してしまうことは、ある意味加害的行為です。どんな相手も事情がある。被害者役になっていた方が楽という視点でそうする場合は。
リレーションシップ2を開催していると、その期間中こういう関連した超分かりやすい学びがやってきます。それはクライアントさんだったり、子どもだったり家族だったり、直接日常で関わる誰かが何かの姿を見せてくれて、底流が何をやっているのかという分かりやすい例を提示してくれます。彼らはそれを私の前で提示することで、私を通して創造主からの変容を求めているのでしょう。リレ2テキストにも書いてありますが、本当に…底流を理解すると自分を理解でき、自分が何者で本当はどんなエネルギーなのかを思い出し、何がしたいのかが分かるのでシフトしていくことが出来ます。
様々な学びに感謝します。